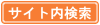2009年度
大会の開催概要
2009年度の研究会は、2/27に予定通り開催されました。予定より大幅に多い102名にご参加いただきました。保田会長による記念講演のほか、10本の研究報告がなされて、参加者との質疑のやりとりが行なわれました。発表内容については、以下の要旨集を参照ください。
大会プログラム・要旨集(2/24版) ⇒ こちら(pdf 0.8MB)
大会プログラム・要旨集+参加者プロフィール集(最終版) ⇒ こちら(pdf 1.8MB)
大会ポスター(A3判) ⇒ こちら(pdf 0.39MB)
大会の開催概要




総会の開催概要
2009年度の総会は研究大会に続けて開催され、36名の会員が参加しました。会費を徴収しないこと、次年度以降の大会も札幌を中心に開催すること、ウェブサイトや研究誌発行のための準備グループをつくることが 承認されました(議事概要を参照のこと)。
また、次年度以降の役員について改選案が出され、承認されました。
総会(2009年度)配布資料 ⇒ こちら(pdf 0.24MB)
総会(2009年度)議事概要 ⇒ こちら(pdf 0.16MB)
2009年度 研究会(大会)
日時:
2月27日土曜日 13時~18時
場所:
札幌市博物館活動センター
札幌市中央区北1条西9丁目リンケージプラザ5階
TEL:011-200-5002 FAX:011-200-5003
アクセス:
公共交通機関をご利用ください。
地下鉄東西線「西11丁目」駅4番出口から徒歩5分。
市電「西8丁目または中央区役所前」電停から徒歩8分。
バス「北1条西7丁目」バス停から徒歩3分。
申し込み:
参加申し込みは2月25日まで。ただし発表希望者は2月15日まで。
以下のことを書いてメールしてください。
・所属・メールアドレス・連絡先(電話)
・懇親会参加の有無、発表の有無
共催:
札幌市博物館活動センター
運営事務局:
事務局、古沢(札幌市)、山崎(札幌市)、持田(北大博物館)
スケジュール(予定)
| 12:30~ | 受付 |
| 13:00~ | 開会の挨拶 |
| 13:10~ | 講演 保田信紀 「大雪山の高山昆虫」 長年、層雲峡博物館・ビジターセンターにおいて高山帯の昆虫類の研究をされてきて、当研究会会長でもある保田さんに話をしていただきます。 |
| 14:10~ | 研究・事例発表会 ※道内の自然史に関する発表です。10件の発表がありました。 |
| 17:50~ | 総会 研究会の今後、役員などについて話します。現会員でない方もご参加ください(入会してください)。 |
| 19:00~ | 懇親会 会費3500円(学生1000円)程度で予定しています。 会場:魚民 西11丁目駅前店 中央区大通西9-3-33 キタコ-センタ-ビルディング地下1階 |
発表一覧
講演 保田信紀 大雪山の高山昆虫松田まゆみ 北海道におけるイソコモリグモの生息実態
山本亜生 銭函海岸の昆虫相―小樽市総合博物館の調査から
内藤華子 石狩浜海浜植物保護センターの活動と課題
義久侑平 札幌に侵入したトノサマガエルがもたらす生物群集への影響
小宮山英重 北海道知床半島でサケ科魚類を採食するヒグマの生態:ヒグマの社会構造と若者組の意味
木下豪太 北海道産ユキウサギの系統地理学的解析
川辺百樹 エゾナキウサギの分布はどこまでわかったか
久井貴世 タンチョウと人との関係史 ―タンチョウの商品化および利用を中心に―
吉野智生 北海道産水鳥類から検出された線虫類の概要と その空間疫学的解析
浅川満彦 保全医学の証憑標本は教育活動にも活用-大学博物館創設への挑戦
要 旨
大雪山の高山昆虫
大雪山の高山帯は広大です。そしてそこには氷期の遺存種と呼ばれる高山性昆虫が日本でもっとも豊かに生息しています。
高山蝶という呼び名は、高山に自生する植物が高山植物と呼ばれたのと同じ発想から生まれてきたものと考えられます。しかし高山帯といっても、一つの定義された高度が存在するわけではなく、北海道より高緯度地域では低くなり、逆に本州の山岳では高くなります。高山帯と亜高山帯との境界はふつう森林限界に設定されています。したがって高山蝶とは、垂直分布的には森林限界より上部の環境(非森林的)で生活する蝶と言えるかもしれません。
北海道には5種(ウスバキチョウ、アサヒヒョウモン、カラフトルリスジミ、ダイセツタカネヒカゲ、クモマベニヒカゲ)の高山蝶が分布していますが、大雪山にはその全てが生息しています。
そのうち本州との共通種はクモマベニヒカゲのみで、残りの4種は本州の高山には分布していません。しかし不思議なことに、海を超えたシベリア大陸や北米大陸にはいずれもその共通種が分布しているのです。この事実は、北海道の自然がいかに大陸と深く関連されていたかを物語っています。
過去の氷期(特に最終ウルム氷期)には海水面が低下したため、日本列島は大陸の一部となっていたといわれています。そのため多くの生物は大陸から渡来していたものと考えられますが、地球が温暖化に向かったとき、まず北海道は津軽海峡によって分離されました(ウルム氷期においても分離されていたという説もある)、しかし比較的に浅い海峡をもつ宗谷海峡や間宮海峡はなおしばらく陸橋として存在しており、その陸橋を通して大陸-サハリン―北海道と生命の交流が続いていたものと考えられます。やがて温暖化がさらに進み、北海道が現在のように大陸と完全に分離されてしまうと北方へと帰ることのできなくなった多くの寒地性の生物は寒冷な気候条件を求めて高山へ高山へと昇りつめていき、今、私たちが「氷河期の落とし子」と呼んでいる高山蝶や高山植物もこのような路を辿ってきたのでしょう。
さらに大雪山の高山帯にはウスバキチョウやアサヒヒョウモンなどのように大雪山のみにその分布が限られている高山昆虫が生息していますが、このような昆虫は、その後の温暖期(ヒプシ・サーマル、約5000~6000年前、現在の気温より2℃ほど上昇していた)に重要な影響を受けていたものと考えられます。例えば、日高山脈のような細い稜線上に高山帯を持つ高山や羊蹄山や利尻山などの孤立した高山では、気温が上昇したとき高山帯域の分断や縮小が起こり、それに対応して高山昆虫の生息地は分断、縮小、さらに消失が起こり、地域によっては個体群の絶滅が生じたと考えられます。しかし比較的に標高も高く広大な連続した高山帯域を持つ大雪山では、多くの高山性昆虫の避難地(refugia)は残されており、その後の気温の低下とともに再びその分布域を拡大することが可能であったのでしょう。
大雪山の高山蝶の生い立ちはこのような地史的背景をもとに形成されてきたものと考えられますが、同じ大雪山系の中でもこのような類似の分布様相はみられます。また高山昆虫と高山植生との対応において、最も特徴あるのは高山風衝地群落における昆虫相です。ここでは、ウスバキチョウ、ダイセツオサムシ、さらにクモ類のアシマダラコモリグモ、ダイセツカニグモなどの真正高山種からなる大雪山特有のファウナが豊かに観察されます。
北海道におけるイソコモリグモの生息実態
イソコモリグモとは
イソコモリグモLycosa ishikariana (S. Saito 1934)は、故斎藤三郎氏が1934年にTarentula ishikariana (和名イシカリドクグモ)として新種記載したコモリグモで、記載に用いられた標本の採集地はishikariとされており、石狩浜がタイプロカリティ―と考えられている。 日本固有種で、北海道と本州の青森県から島根県までの日本海沿岸および青森県から茨城県までの太平洋沿岸の砂浜に生息する。コモリグモとしては大型で、体長は雌が20mm前後、雄が17mm前後。海浜植物がまばらに生育する砂浜に縦穴を掘って中に潜み、夜間に巣穴付近を通る昆虫などを捕食する。昼間は巣穴の入り口を、砂粒を綴って閉じていることもあるが、子グモは入り口を閉じないために昼間でも見つけやすい。また、古巣の有無も本種の生息を調べる際のポイントとなる。 海浜植物を伴う自然の砂浜の激減により生息地が減少しており、国のレッドデータブックで絶滅危惧Ⅱ類(VU)とされる。
八幡の生息可能性浜の推定と生息の実態
八幡(2007)は、イソコモリグモの減少についての量的評価を行なうことを目的に、本州での実地調査のデータを利用して統計モデルを作成し、そこから全国における「生息可能性浜」と、生息域の減少について推定を行なった。その結果、北海道においては推測生息浜長が621.7キロメートル、そのうち高レベル浜が459.3キロメートルとなり、北海道では広範囲にわたって本種にとって良好な生息環境が保たれていることを示唆した。 演者らは渡島半島、知床半島、根室地方を除く海浜の実地調査を行った結果、生息推定浜長は約225キロメートルとなった。八幡(2007)の推測が過大となった理由は、自然砂浜の中に本種の生息不可能な海食崖地形が含まれているためと考えられる。
イソコモリグモの危機と保護の視点
本種の生息地の減少要因としては港湾建設、海岸浸食による段丘化、浸食防止の護岸や波消ブロック、車の乗り入れや人による踏み荒らしなどが挙げられる。孤立した生息地、小規模生息地ではモニタリングの強化や要因分析を行い、早急に保護策を講じることが求められる。また、大規模生息地では護岸工事などの改変の把握と工法の検討が求められる。
銭函海岸の昆虫相―小樽市総合博物館の調査から
石狩川河口を中心に約25㎞にわたって広がる「石狩砂丘」は、都市近郊にありながら、砂浜海岸特有の景観、生態系が良好な状態で残る、貴重な自然海岸である。小樽市銭函3–5丁目の海岸は、その中でも特に自然度の高い場所の一つであるが、これまで生物相に関するまとまった調査・研究はほとんど行われてこなかった。演者が勤務する小樽市総合博物館では、小樽市内に生息する動植物のインベントリー調査を続けているが、2004年からはこの銭函海岸を調査地に設定し、主に昆虫相の調査を実施している。
調査地について
本調査は新川河口右岸から樽川埠頭までの約5㎞の海岸を調査範囲とし、生息する全昆虫のリスト作成を目指している。調査地は汀線に沿って幅30~200mほどの砂丘が帯状に続いているが、近年は浸食が進み、海側の段丘化が著しい。砂丘にはハマニンニク・コウボウムギ・ハマナスなどを主体とした海浜植生が広がり、内陸に向かってススキ等が優先する自然草原、カシワ海岸林と段階的に植生が変化する。また、砂丘の凹地には小規模な湿地が点在し、新川河口右岸の小樽内川跡にはやや大きい開放水面とヨシ群落がある。
これまでの成果
これまでにトンボ目、鞘翅目、半翅目に関する3本の報告を発表し、約250種を記録した。未発表、未同定の標本は多数あり、未発見のものを合わせると、おそらく1000種ほどの昆虫が本地域に生息していると思われる。
海岸性、草原性、湿地性、カシワ依存の特徴的な種が数多く確認され、レッドリスト掲載種も17種に及んだ。また、北海道でほとんど記録のないものや、既知種と形態・生態が異なっている不明種などもいくつか発見されており、今後の興味深い検討課題になっている。
これまでに確認された鞘翅目・半翅目を生息環境ごとに整理すると、海岸18種、草原65種、湿地48種、森林71種となり、異なる環境に依存する種がまんべんなく得られていることが判る。それほど広くない調査範囲からこのような結果が得られたことは、本地域の昆虫相の高い多様性を示していると言える。また、汀線から内陸に向けて変化する砂浜海岸特有の環境構造が、良好に残存していることも示している。
今後の課題
汀線付近で採集された昆虫については未同定のものが多い。海岸環境を検討する上で重要な要素であるので、専門家と協力して解明度を上げる必要がある。また、昆虫の種数で大きな割合を占める鱗翅目、膜翅目についての調査が遅れている。これらは訪花昆虫としても重要であり、海浜植生、カシワ林など各環境で状況の把握を進めたい。
本地域は砂丘の浸食、車輌乗り入れによる植生の破壊、不法投棄、開発などにより、環境の悪化が近年著しい。しかし市域のはずれにあることからこの地域に関する小樽市民の関心、認知度は決して高くない。今後も情報の収集、公開を続け、多くの人にこの場所と、置かれる状況について知っていただくことが重要だと考えている。
石狩浜海浜植物保護センターの活動と課題
石狩浜の自然と海浜植物保護センター
石狩砂丘は、小樽市銭函から石狩市厚田区無煙浜まで約25kmに及ぶ海岸砂丘です。汀線から砂浜、海浜植物に被われた海岸草原、海岸林と、海岸砂丘特有の植生の帯状構造が見られ、そこには砂丘植生に依存する生き物が数多く生息し、猛禽類や中型哺乳類を頂点とする生態系が維持されている、全国的にも貴重な自然海岸です。このうち、石狩湾新港から石狩川河口までの約7kmの部分が石狩浜です。
1970年代以降、過剰なレジャー利用やハマボウフウ等山菜採りなどにより、海浜植生の破壊が進み、これを危惧した地元市民や自然愛好者の後押しにより、石狩浜海浜植物保護センターは、2000年にオープンしました。石狩浜の豊かな自然を守り回復させ、みんなの財産として次の世代へ残していくための活動拠点として、石狩浜の自然環境保全に関する普及啓発活動や調査研究に、市、市民、研究機関が協働で取り組んでいます。
おもな活動
・普及啓発:自然観察会、こども自然教室、ボランティア育成講座、学校等学習指導、
情報誌・HP・展示物等での情報発信
・調査研究:植生回復試験、定期観察による開花状況調査、植生モニタリング、
動植物リスト作成等
・保全対策:海浜植物等保護地区の管理・監視、
一般海岸・海岸保全区域等のロープ柵の設置・管理等、
海岸管理者との調整による保全
課題
レジャー利用者のマナー不足・一般的な海浜環境への認識不足
/------------------------------------------
アピールすべき海辺環境保全の必要性
・海浜生態系の有益性:緩衝機能、飛砂防止、等
・自然海浜の希少性:全国の砂浜海岸の7%
(全国1300箇所の砂浜海岸のうち人工物なく6種以上の海浜植物生育する海岸の割合、
日本自然保護協会調査より)
・希少種絶滅危惧種の生息地(植物10種、野鳥17種、菌類1種)
・海浜特有の生物の生息地(海浜植物、昆虫類、菌類など)
・多様な生物相の生育生息地(植物300種、野鳥142種、菌類29種記録)
・自然海浜に関する環境学習の場
------------------------------------------/
札幌に侵入したトノサマガエルがもたらす生物群集への影響
はじめに
トノサマガエルRana nigromaculataは本州ではレッドリストに記載される地域があるほど希少な種となっているが,北海道では1990年頃に初めて北広島の水田で発見され,2004年に制定された「北海道ブルーリスト」において,国内外来生物に指定された.近年になってもトノサマガエルの分布は拡大し,現在では札幌市,江別市,恵庭市,南幌町でも確認されている.
本研究の調査地である平岡公園の人工湿地では,2000年の完成当初からトノサマガエルの生息が確認されていた.人工湿地ではゲンゴロウCybister chinensisやオオコオイムシAppasus majorなどの希少種の生息も確認されているが,現在ではトノサマガエルが繁殖場所として利用している.外来生物による生態系への影響の種類は様々であるが,カエル類では生きた動物を採餌する種が多く,捕食による被害が懸念される.
そこで,本研究では在来生物群集への影響を把握するため,札幌市において外来生物であるトノサマガエルの食性調査を実施した.
方法
2008年に調査地内で捕獲した324個体のうち,空胃であった194個体を除く130個体から摘出された胃内容物は743となった.
結果・考察
胃内容物の解析結果で,4門8綱18目という多種多様な動物種をトノサマガエルが捕食していることが判明した.そのうち79.1%が節足動物であり,昆虫綱,ヤスデ綱,ムカデ綱,クモ綱,甲殻綱の5綱を含んでいた.特に昆虫綱は総数の66.8%を占めており,最も多く捕食されていた.節足動物以外では,淡水産・陸産の貝類が19.5%,ミミズ類が1.2%,ハリガネムシ類が0.1%であった.
昆虫類においては,少なくとも65種の昆虫が捕食されていることが判明した.捕食された昆虫のなかには,希少種であるオオコオイムシも含まれていた.なお,ゲンゴロウについては摘出された胃内容物には含まれていなかったが,幼虫が蛹化場所を探すために陸地に上がったところを数匹のトノサマガエルに襲われ,捕食される現場を目視により確認した.摘出された胃内容物の季節消長を調べた結果,各餌種の出現頻度が季節によって変化していることも判明した.
本研究では,札幌市内におけるトノサマガエルは特定の餌動物に依存せず,身の回りの動くものを非選択的に捕食する「何でも屋的捕食者」であることが判明し,在来の生物群集に少なからず影響を与えていることが示唆された.
北海道知床半島でサケ科魚類を採食するヒグマの生態:ヒグマの社会構造と若者組の意味
2004~2009年までの6年間、毎年8~11月に北海道知床半島ルシャ地区でサケ科魚類(カラフトマス・シロザケ)の生魚や死魚を採食するヒグマの行動を記録した。観察は、日の出前から日没後までの間の日中、目視可能な光条件下で自動車の中から実施した。ヒグマが観察車の動作範囲を予測して観察域内で不安感なく生活することを期待して、観察には同一の自動車を使用し、線状に固定した経路を移動して行った。調査域内にはサケ科魚類が海から遡上し、自然産卵で再生産している川が3本流れている。これらの河川は、河口部からサケ科魚類の産卵域となっている。そのため当調査域では産卵前の脂の乗った個体から完熟卵を抱えたメス、産卵後の自然死間近の個体などが混在して遊泳しているという特長があることにくわえて産卵最盛期経過後は大量の自然死個体が出現する場所になっている。ヒグマの食材の対象となったのはこれらすべての状態のサケ科魚類で、河川中や海中、およびその周辺で捕獲・拾得した生魚、死魚およびその破片(斃死魚、動物が捕食後の死骸、発酵・腐敗したもの、乾燥したもの)など多様であった。204日間で(年平均34日)、のべ約80頭を個体識別して行動を記録した。ルシャ地区で観察したヒグマは、人との距離に一定の線を引きながら採食にかかわる行動を観察させてくれる個体と採食行動の観察をさせず人の目から遠ざかることを最優先する個体すなわち行動観察をさせてくれない個体に分けられた。これらの人や車と出会った後の行動の違いから前者をA型(Actor type)のヒグマ、後者をN型(Normal type)のヒグマとして区別して記録した。この報告は、A型のヒグマの行動の記録である。
ヒグマは母と子で構成された親子熊以外は単独生活者といわれている。観察した結果、基本的には単独生活者であるが、一定のルールで集団を形成することが判明した。個体識別をしてこれらの集団の構成員を分析すると、2から4頭で構成された親子(子の年齢は0歳~2歳)、母熊から独立した兄弟(1歳~2歳)、若者組(1歳~3歳)、大人組(4歳以上)の4グループに分けられた。兄弟は日中および夜間も行動を共にしていた。しかしながら、若者組は日中のみ一緒に過ごす集団で、夕方までには集団を解消すること、主に同年齢の個体で構成されることが判明した。また大人組は若者組ほど密着した行動様式は示さないが、排除する行動をおこなわず、採餌場所や休憩場所に一緒にいることを許容する程度の絆が継続している集団と推定された。
大人は単独生活者であることが基本であるヒグマが若者組を形成する意味は、クマ社会では弱者に位置づけられる母親から独立したばかりの発育段階の時期に個体の生存率を高める役割を担う生存戦略のひとつと推定される。
北海道産ユキウサギの系統地理学的解析
北海道にはユーラシア大陸北部に広く分布するユキウサギ(Lepus timidus)の固有亜種エゾユキウサギ(L. t. ainu)が生息している。エゾユキウサギは形態的特徴により亜種に分類されているが、北海道産ユキウサギと他地域集団との遺伝子情報に基づく系統関係は十分に調べられていなかった。また、現在いくつかの哺乳類で北海道内での遺伝的多様性が調べられており、それぞれの種が特異的な集団遺伝構造を持ち、各々の歩んできた集団史を反映していると思われる。そこで本研究では北海道産ユキウサギの遺伝子解析を行うことで大陸集団との系統関係が明らかにし、また北海道内での遺伝的集団構造を調べることで北海道産ユキウサギの集団史について考察を行った。
本研究では2009~2010年に北海道84地点で採集したユキウサギの糞を材料に、DNA抽出の成功した63地点(72個体分)についてmtDNAの解析を行った。
先行研究により大陸の集団についてはスカンディナビアなどのヨーロッパ北部の地域個体群と、沿海州やカムチャツカなどロシア極東といった非常に距離の離れた地域間でも遺伝的な差はほとんど見られないことが知られており、大陸の集団は最終間氷期以前(およそ16万年前)に多様化して以降、個体群間で遺伝的な交流が続いていると考えられている。しかし本研究によって北海道のユキウサギは大陸集団とは遺伝的にも独立した系統集団であり、その起源も比較的古いことが明らかになった。
また今回、北海道のユキウサギと朝鮮半島の固有種L. coreanusが近縁関係であることが示された。これは過去に北海道産ユキウサギの祖先集団とL. coreanusの間で種間交配が起こったためであると推測される。
一方、ユキウサギの北海道内における遺伝的多様性を調べたところ、北海道には集団構造の異なる2つのmtDNAグループ(Gp1,Gp2)に分けられることが判明した。さらにGp1は北海道全域に分布しているが、Gp2は石狩低地帯より東の地域でのみ確認されGp1に比べ遺伝的多様度も低く、比較的若い集団であることが分かった。このような遺伝的集団構造のことなる2つのmtDNAグループの存在は、北海道内で過去に大きな集団サイズの縮小や生息域の分断化が起きたか、または北海道への移入が複数回あったことを示唆していると考えられる。
以上のように本研究によってこれまで未解明であった北海道産ユキウサギと大陸集団との系統関係や北海道内での特異な遺伝的集団構造が明らかになった。今後この集団構造の形成要因について北海道内で起きたイベントや大陸との交流をより詳しく検証することで、北海道の生物相全体の構造や歴史の理解に役立つと期待される。
エゾナキウサギの分布はどこまでわかったか
近年刊行された著作物(例えば“The Wild Mammals of Japan”,「日本の哺乳類改訂版」)においても,エゾナキウサギOchotona hyperborea yesoensis の生態的分布や地理的分布に関して不正確な,あるいは曖昧な記述がみられる.そこで,本種の分布に関して得られている情報を整理し,知見の共有化をはかる機会としたい.また,今後の本種の分布研究の課題についても明らかにしたい.
生態的分布に関する知見の整理
Inukai and Shimakura(1930)以来これまでに得られた知見から,本種の分布が岩の積み重なった空間(以下「岩塊堆積地」)の存在によって支配されていることは疑いない.演者は,本種の生息可能な岩塊堆積地が主に崖錐(talus)と自破砕溶岩(autobrecciaed lava)に由来することを明らかにした(川辺2008). この岩塊堆積地の出現要因を理解することは重要である.これにより未調査地域での生息地の予測精度を高めることができるからである.本種の生息空間の記載は,これまで岩場・岩礫地・岩石地・ガレ場・露岩地など著者の好みで行われてきた.これからは,地形の由来を考慮した記載をすべきである.因みに米国の“The Smithsonian Book of North American Mammals”では,Ochotona collarisの生息地をareas of talus slope or broken rockとしている.
地理的分布に関する知見の整理と分布を制限する要因
本種は,1929年に北海道中央部の置戸町の森林地帯で確認され (Inukai and Simakura 1930) , 1930年代初頭までに大雪山系の高山部(Inukai 1931),夕張山地・日高山脈での生息が判明した(Inukai 1932).その後,北見山地の広い範囲から生息が確認された(内田1960). 1988年には北海道環境部自然保護課によってアンケート調査が行われ,これにより本種の北海道における地理的分布がほぼ明らかになった(小野山・宮崎1991).すなわち,本種は,北海道中軸部の山岳地帯である北見山地・大雪山系・日高山脈・夕張山地に生息し,垂直分布は幌満の標高50mから大雪山系白雲岳の標高2230mに及ぶ.
北海道東部の阿寒や知床の火山群・北海道西部の暑寒別火山や石狩低地帯以西の山岳等にも岩塊堆積地はあるが生息していない.これには,現在の分布域からの距離とこれらの地域における岩塊堆積地の規模が関わっていると考えられる.また,本種が「高山のような涼しい場所でのみ生きていける」(石黒2007)との見解は,分布実態から否定される.つまり北海道における本種の地理的分布は,気温や高度ではなく岩塊堆積地の集中度合いによって制限されている.
今後の課題
本種の生息地が極めて少ないといわれてきた夕張山地に少なくない生息地がある(川辺2009)ことを,そして夕張山地と日高山脈を繋ぐ生息地が存在することを今後明らかにしたい.また,本種が生息していた,あるいは生息していたと推測される低標高地の生息地破壊の実態を明らかにし,レッドリストに本種を登載すべきであることを示したい.
付記 ここで述べたことの多くは,演者の論文「北海道におけるエゾナキウサギの分布」と「夕張山地におけるエゾナキウサギ生息地」に基づいている.
タンチョウと人との関係史 ―タンチョウの商品化および利用を中心に―
はじめに
タンチョウGrus japonensisは,絶滅の危機にあったことから,1952年に国の特別天然記念物に指定された鳥類である.かつては本州方面でも見ることができた渡り鳥であったが,現在は主に北海道東部でしか見ることができない.北海道においては,明治中期頃まで北海道内各地に広く分布していたことが様々な資料から推測できる.北海道のタンチョウは,明治の混乱期における乱獲や湿地の開発による生息地の減少などが原因で,明治後期には絶滅したとまでいわれていた.しかし,その実態については未だ十分に解明されているとはいえず,今後のタンチョウの保護管理を適切に行うためにも,これまでのタンチョウと人との関わりを再確認する必要がある.本発表では,タンチョウを減少させた要因のひとつとして考えられる「商品化および利用」に焦点をあて,その利用実態について文献調査を中心にまとめた.
Ⅰ.日本におけるタンチョウ
古来よりタンチョウは縁起の良い瑞鳥とされ,かつては本州方面でも見ることができた鳥であったことから,タンチョウと人は様々な場面で関わり合ってきた. 青森県や鳥取県などでは,古代の遺跡からタンチョウの骨が出土し,骨器の素材や食料としてタンチョウを利用していたことが推測できる.奈良時代には,貴族の屋敷でタンチョウが飼養され,平安時代には,ツルを食材とした料理が見られるようになる.ツルを最上位の食材・贈答品として頻繁に用いるようになるのは室町後期以降であり,これは,織田信長や豊臣秀吉らが,己の権威の象徴としてツルを利用しはじめたことによる.そして江戸時代には,ツルは将軍や有力大名など位の高い者の鳥とされ,庶民による捕獲や売買は厳禁,違反者には罰が科せられた.食材・贈答・飼養など様々な場面でタンチョウが利用され,鷹狩における最上の獲物としても位置付けられていた.
Ⅱ.蝦夷地・北海道におけるタンチョウ
各種資料により,タンチョウは,明治中期頃まで北海道内各地に広く分布していたと推測できる.アイヌの人々はタンチョウを“湿原の鳥”と呼び,タンチョウにまつわる口承文芸なども伝えられている.また,アイヌの人々が捕えたタンチョウは,交易や儀式を通じて和人へももたらされた. 蝦夷地では,タンチョウを塩漬けにして他国へ輸出したなど,「鶴」は蝦夷地の産物として様々な文献に記されており,このことから,蝦夷地のタンチョウは重要な商品として利用されてきたと考えられる.贈答品としての利用も多く,徳川光圀へタンチョウを贈ったとの記録も残されている.
タンチョウの商品化と利用は,明治時代の北海道においても続けられてきた.この時代では,庶民による利用のほか,1894年には,現在の北広島市で捕獲したタンチョウを明治天皇へ献納した記録なども残されている.しかし,『開拓使事業報告』によると,1873年~1881年の9年間での産出数は60羽程度であり,その数はさほど多いとはいえない.
おわりに
古来よりタンチョウは,道具や料理の素材,商品や贈答品,あるいは愛玩動物などとして,様々な場面で人間に利用されてきた.特に江戸時代以降は活発な利用が行われ,かつて蝦夷地に数多く生息していたタンチョウも,蝦夷地の重要な産物として位置付けられた.蝦夷地では,本州方面への輸出が活発に行われていたと考えられ,江戸期を通じて利用の記録がある.さらに,ツルは明治期の北海道においても産物として利用されていたものの,その産出量はさほど多いとはいえない. このことから,北海道におけるタンチョウは,明治に入る頃にはすでに相当数捕獲され,その生息数も減少していたと考えられる.したがって,タンチョウ減少の要因は「明治の混乱期における乱獲」だけでなく,江戸期から続く活発な利用も影響していたと推測される.
北海道産水鳥類から検出された線虫類の概要と その空間疫学的解析
北海道は東アジア産水鳥類の中継地や越冬地として重要な役割を果たしている。しかし、近年は生息地の減少や環境悪化などにより、限られた生息地への一極集中とそれに伴う感染症、寄生虫症の発生リスクの上昇が指摘されている。演者らは2003年以降、酪農学園大学野生動物医学センター(WAMC)に収容された水鳥類について、寄生線虫類の保有状況の記録およびその分布特性を明らかにする試みを行っており、今回はその概要について報告する。検査対象としたのは計4目7科38種324個体に属する水鳥類であり、それぞれ道内各地で死体回収或いは傷病鳥として保護収容後に死亡したものであった。検査個体は計測、解剖後に全臓器を実体顕微鏡下で精査し、寄生虫を検索した。得られた線虫類は70%エタノールにて固定後、ラクトフェノール液を用いて透徹し、形態および計測値に基づいて種を決定した。検査個体の64.2%から計27種の線虫類が検出され、多くを新宿主、新産地として記録した。検出された種のうちCyathostoma lari, C. microspiculum, Amidostomum fulicae, Epomidiostomum crami, E. uncinatum, Porrocaecum semiteres, Inglisonema sp., Madelinema sp.およびSkrjabinoclava horridaは国内初記録であった。また検出された種の中には、家禽および野生個体での致死症例や若齢個体の大量死の報告があるAmidostomum, Epomidiostomum, Cyathostoma, Contracaecum, Streptocara, Echinuria, Sarconemaの各属線虫が含まれており、国内の水鳥類の保全を考える上でこれらの高病原性線虫類の保有状況を把握しておくことは重要であると考えられた。そのため、収容位置情報が明確であった個体の緯度経度情報を基に、空間配置パターン分析の手法の一つであるK関数法を用い、線虫の地理的分布特性について予備的に検討を行い線虫症の発生予測モデルの構築を試みた。その結果、寄生虫種によって形成するクラスタが異なり、広域分散型、凝集型、ランダム分布型等の傾向が認められ、この手法は寄生虫症の発生や分布状況の把握に有効であることを示した。現在、これら寄生線虫の分子生物学的解析手法を組み合わせ、より簡便な手法を検討中である(Yoshino et al., in submitted)。
本研究の主眼は(獣医学の主対象である)個体レベルではなく、(進化学的な単位である)個体群レベルであり、その健康管理の応用に向けての初めての模索である。そのためには、線虫以外の寄生虫や他の病原体あるいは他の動植物の地理的分布状況や生息地の人為的な影響などの情報も重要であり、当然ながら、生態・進化など自然史的な側面は不可欠である。本研究会諸兄との今後の実りある連携を期待したい。
本研究は文科省戦略的研究拠点事業(酪農学園大学大学院獣医学研究科)および同・科研費基盤研究 (18510205, 20380163)の助成を受けた。
保全医学の証憑標本は教育活動にも活用-大学博物館創設への挑戦
自然生態系や生物多様性の保全は世界的な潮流で、獣医学、医学および保全生態学との学際領域として保全医学が新興し、新興感染症や生態系への脅威として外来寄生虫などの調査が急増している。また、一般家庭では確実に飼育不適で、外来種問題の源ともなるエキゾチック・ペットの輸入数も急増している。さらに、希少動物の保護拠点として動物園や地方産業の振興のための特用家畜飼育など、人間社会に近接して存在する動物の多様化傾向は著しい。その傾向に比例するかのように、獣医学や応用動物分野の研究分野にあっても、多様な動物を対象する傾向を強め、たとえば酪農学園大学にあっても、動物学データベースでヒットする論文の七割強が、陸上脊椎動物(爬虫類、鳥類、哺乳類)を宿主とした微生物(ウイルス・細菌)・寄生虫学領域あるいは衛生動物・昆虫学領域などの保全医学に関わる。また、保全医学にあって、感染症・寄生虫症対策や宿主-寄生体関係の把握といった分野の比率は、世界的な関連学会や専門職大学院の教育課程を眺めても非常に高い。
しかし、このような詳細な寄生体の保有状況調査が実行されても、宿主グループの分類が現在論議中である場合(例:トガリネズミ類、ヤチネズミ類、イタチ・テン類など)、 近縁亜種が人為的に野外に放逐される場合(例:シマリス、キタリス、メジロ、オオタカなど)、野生下で雑種化が稀ではない場合(例:野生カモ類間、アイガモとマガモ間など)などでは、あやふやな宿主情報では、宿主-寄生体関係の生態・進化・生物地理などの研究遂行で、誤った結論に達する危険性を孕んでいる。また、疫学調査では宿主の年齢・季節や分布域など時空間に関する宿主個体の情報が不可欠である。たとえ、調査結果の公表時点であやふやな宿主情報ではあっても、宿主標本が完備しておればある程度の再検討が可能となる。
そこである宿主-寄生体関係が、特定の時・空間に分布したことを示す証憑が標本化される必要がある(voucher specimen(s))。通常、寄生虫学や野生動物の疾病分野における証憑標本とは、寄生虫/病原体自体の標本化についてのみ用いられる。疫学調査や宿主-寄生体関係の生態研究では、調べた動物に目的とする寄生虫あるいは病原体が「不在」であるという情報も重要であるが、不在証明された動物は、当然、宿主とは見なされず、記録すら残らないことがある。可能ならば、これら「調査対象動物」も同じく証憑標本化すべきである。疫学調査で対象とされる宿主あるいは対象動物の標本化などは皆無に近い。研究費、スペース、労力などが非常に限られた研究環境では、現実的に困難であることは想像に難くないが、2004年、酪農学園大学に保全医学研究拠点、野生動物医学センターWild Animal Medical Center (WAMC)が開設されたのを機に、この証憑標本を残す試みを継続している。
この試みは困難の連続である。が、大学とは「研究を基盤にした教育」をする組織であることを明確化すれば、このような標本も有効な教育(啓発)に還元されれば、いつの日か大学博物館の創設などに繋がるものと信じている。今回はその挑戦の概要を紹介したい。